二次相続以降の相続対策
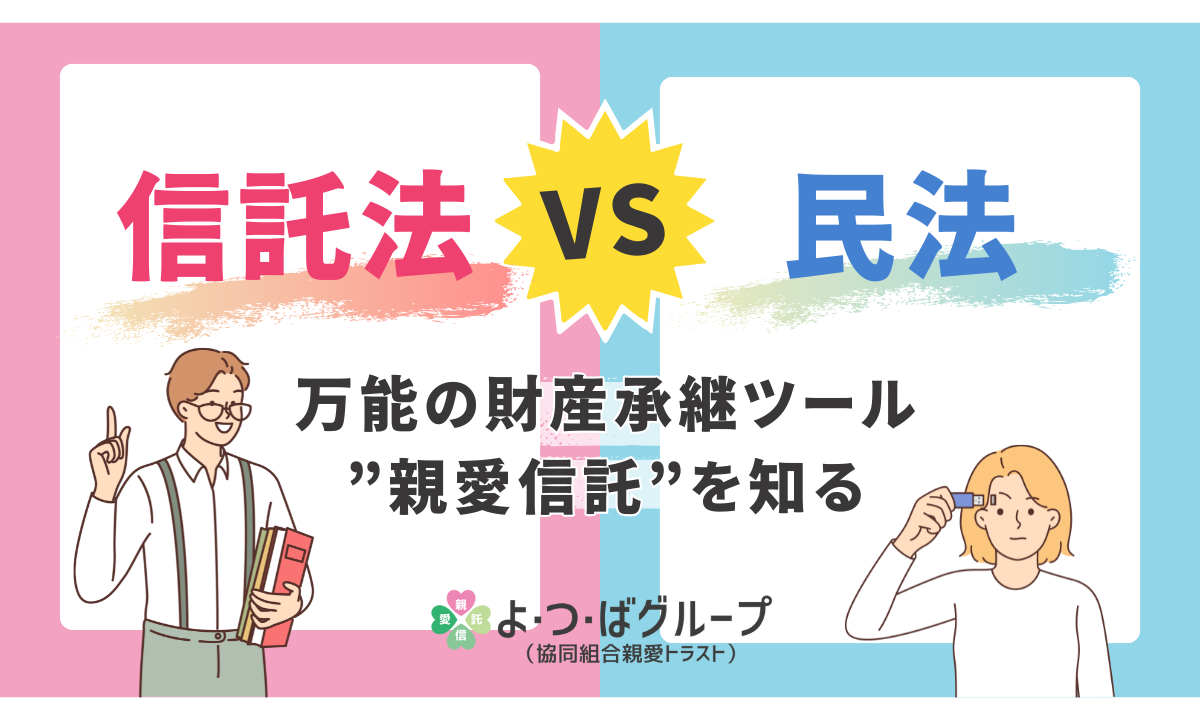
同業者(司法書士・行政書士)の方と信託のお話をすると、よく「信託は難しい」というご意見をいただきます。
実際、私もよ・つ・ばに入会する以前に、何度か信託の相談を受けていろんな書籍等を参考にして契約書を作成してみたことはあるものの、どこまで理解していたかは怪しいです(結局、押印までには至らず)。
よ・つ・ばに入会してネットやリアルのセミナーなどで研鑽を重ねていくうちに自然と身についてきた感じです。
信託の理解を難しくしているもの、それはやはり「民法」だと考えます。
司法書士試験、行政書士試験あるいは司法試験といった法律系の資格試験には民法が大きなウエイトを占めますので合格のためにはどうしても民法の理解はマストなのです。
しかし「民法脳」のままでは信託法の理解の妨げになりかねません。
親愛信託契約により特定の財産を信託すると、その財産は「信託法」の世界に移ります。
ところが残念なことに「信託した財産の所有権は委託者から受託者に移転する」という民法的な発想を持っている法律専門家が少なくないように思えます。
「信託では所有権は移動しない」
このことが信託の理解の第一歩なのではないかと考えます。
むしろ、これが腑に落ちれば信託の本質が理解できたと言っても過言ではないかも知れません。
親愛信託契約では、当初受益者が死亡した時にその受益権は消滅して、二次受益者が新たな受益権を取得する、という条項を置くことになりますが、この受益権の移動を「相続」とみなして「遺留分」の対象になる、という意見も少なくありません。まさに民法の発想ですね。
しかし、よくよく考えると「遺留分」というのも不思議な制度です。
本来的には個人の財産権は日本国憲法で保障されているとおり、個人の財産を誰に渡しても自由なはずですが、本人の死亡後は本人の(法律上の)相続人の生存権が個人の財産権に優先してしまっているのですから。
話変わって、私が遺言の相談を受けたとき、推定相続人が兄弟姉妹だけあるいは一人もいない場合でなければ、依頼者に対して必ず遺留分の説明をしなければなりませんが、中には相続人の中に財産を一円も渡したくない相手がいる、というケースも最近増えてきています。
確かに、家庭裁判所に「推定相続人の排除」を申し立てて相続人から除外する方法もありますが、認められることが少なく(令和4年度で約2割)、また排除が認められてもその相続人の直系卑属に相続分が代襲します。
そのような方に信託では相続と違って遺留分は考えなくてよい、とお話すれば大変興味深い反応を示してくださります。
ですが、100%完璧とは現段階ではお話できないのも事実です。
「信託受益権に遺留分侵害額請求権は及ばない」という判例がまだ出ていないからです。
実務的には遺留分を請求され、支払わざるを得なくなった場合に備えて遺留分支払いの原資を生命保険などを活用するなどして準備しておく、という手当をしておきます。
仮に今裁判になったとしても、信託が遺留分に勝てるのか?というと、個人的には簡単ではないと考えます。
私もそうであったように、「遺留分はあって当然」という考えの法律専門家は少なくないからです。
でも、あってはならないことですが、信託が遺留分に負けてしまったら、信託が普及しなくなるのではないかと危惧してしまいます。しかし、法律は法律家が変えるものではありません、「国民」が変えるものです。
私が法律専門職となってから、いくつかの違憲判決が出されました。
例えば、非嫡出子の法定相続分が嫡出子の2分の1であるという規定が違憲とされたのも、日本において法律婚が必ずしも絶対でないという考え方が育ってきたからと考えます。また、昨年では同性婚を認めないという民法や戸籍法の規定が違憲という判決が高裁で何件か出されています。こちらも、結婚の在り方が変わってきたことが少なからず影響されていると考えています。
同じように、多くの日本人が、自らの財産の承継についてより真剣に考えるようになれば、自らの財産を自らの希望通りに引き継がせたいという強い想いが、戸籍上相続人であるというだけで遺留分を主張できるようないわゆる「笑う相続人」よりも尊重してしかるべき、そんな時代が来ると信じます。
そうなれば、「信託受益権に遺留分侵害額請求権が及ばない」という最高裁判決が出されるのではないかと考えます。
そのためにも、万能の財産承継ツールである親愛信託を一人でも多くの人に知っていただき、ご活用いただくべく、自己研鑽と啓蒙に励む所存です。
令和7年4月4日
一般社団法人よ・つ・ば民事信託協会大阪
理事 田村充弘