事業承継対策
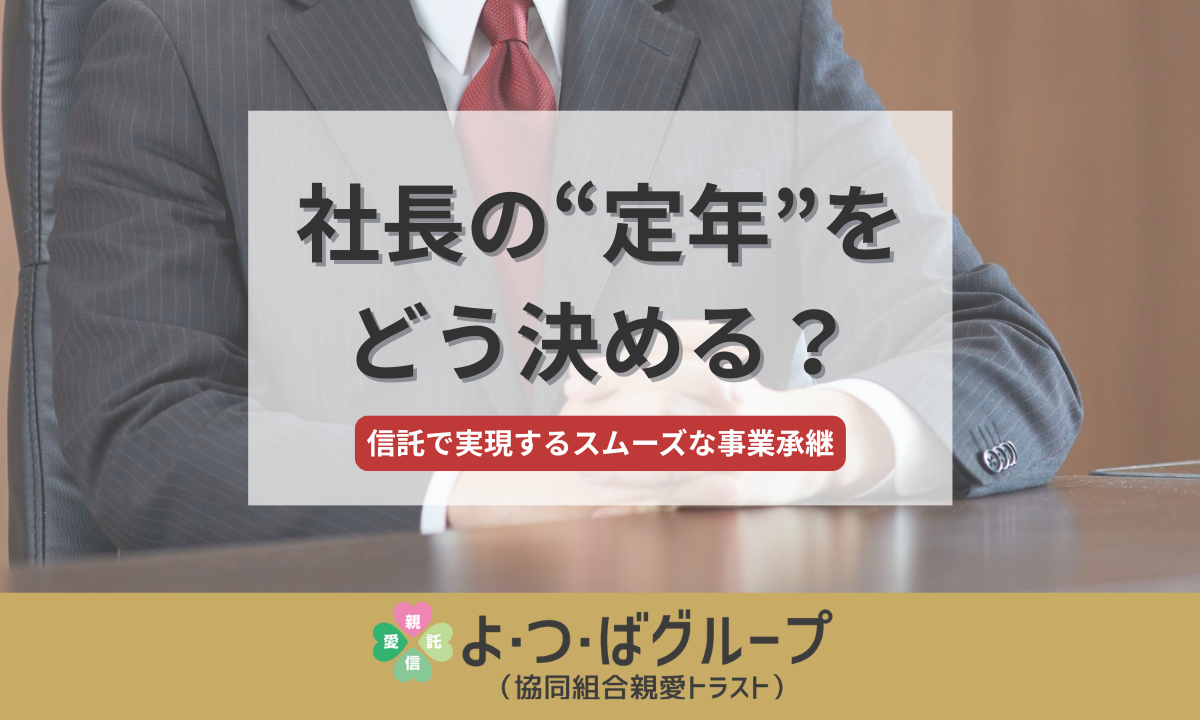
~親愛信託®(家族信託®・民事信託)を活用する方法~
現役社長さんが、いつ自分は引退しようか?誰に継がせようか?と考える時が来ると思います。
サラリーマンであれば、定年が制度としてなくなった会社が多いとはいえ、60歳や65歳というような一定の決まりがあります。
一方で、自分が会社を経営している場合、いつ自分が会社を退くのかを自分で決めなければいけません。
理想を言えば、自分のことであっても、事前に「定年」を決めておくべきだと思います。
80歳くらいになって、跡を継ぐ人もいなくて、仕方ないからM&Aにしようかとあわてて動き始めるというのではなく、もっと計画的に行うべきです。
誰も後を継ぐ人がいないのではなく、もしかしたら継がせるタイミングを逃してしまっている可能性もあります。
会社に入社した時から定年が決まっているように、法人を設立した時に自分の「定年」を決めておき、それが計画通りに実行できるようにしておくために 親愛信託®(家族信託®・民事信託) を活用します。
▶受託者の日常業務のポイントを詳しく解説!セミナー詳細はコチラ【10/2締切】
事業承継は株を自分以外の人に譲渡もしくは贈与するという方法で行われることがほとんどだと思います。
このタイミングが難しいので、なかなか事業承継が進まない原因の一つでもあると思います。
自分が経営者としての実権を譲るタイミングに、ちょうどいい株価だとスムーズにいくと思いますが、なかなかそうはいきません。
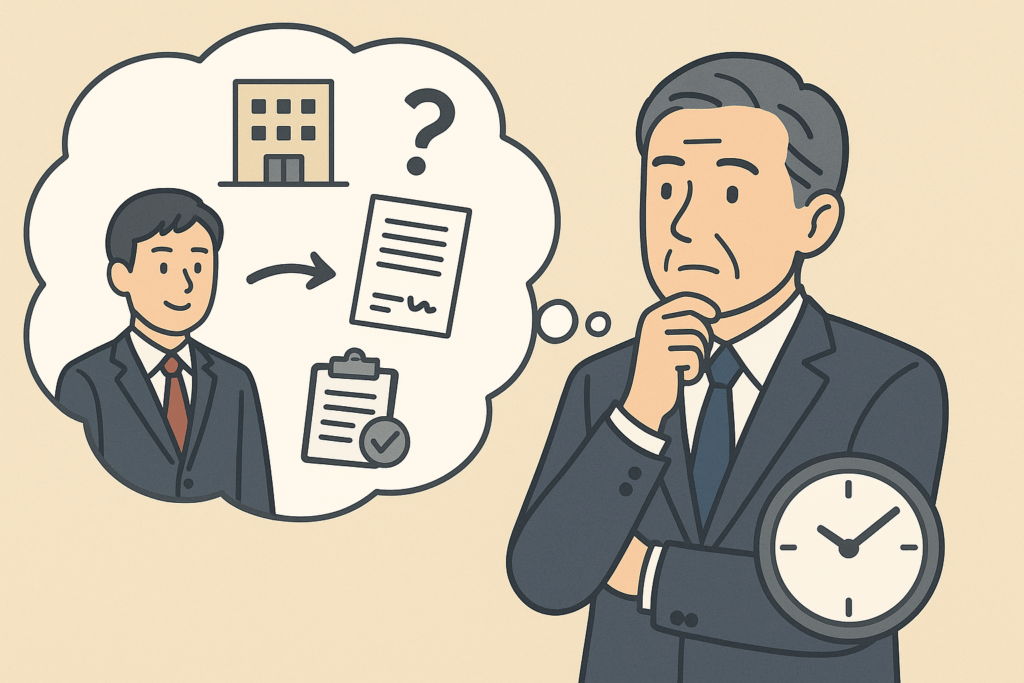
その解決策として、自社株を信託します。
所有権の時は、株の議決権も財産権も所有者が持ちます。
譲渡所得税や贈与税、相続税の対象になるのは受益者が持っている財産権です。
財産権が動かなければ課税はありません。
信託財産にすると株の議決権だけ、後継者に渡すことができます。
いつでも議決権を後継者に渡せるようにしておくためには、自己信託という方法もあります。
自己信託を活用すると受託者になる人がまだ決まっていなくても、信託を活用することができます。
自己信託を活用することで将来の事業承継に備えることができ、タイミングを逃すことなくスムーズに事業承継を行うことが可能になります。
自社株を所有権ではなく、親愛信託®(家族信託®、民事信託)を活用して信託受益権に変えておくことで、スムーズな事業承継を行うことができます。
会社の規模や家族構成、置かれている環境でリスクは異なります。
ご自身に合った信託スキームを作るために、ぜひ一度 よ・つ・ばグループ にご相談ください。
令和7年9月26日
協同組合親愛トラスト
代表 松尾陽子
・経営者必見!親愛信託で会社と資産を安心承継
・不動産の相続、誰に継がせるべき?親愛信託で柔軟に対応する方法
・財産管理も承継も思いのまま!経営者のための親愛信託

行政書士/簿記全商1級/秘書検定2級/FP3級/食品衛生責任者/大型自動二輪
税理士補助・飲食店経営・人材派遣会社経営などを経て、平成27年に行政書士事務所を開業。信託を組成・普及させる任意の団体を作り、28年8月に法人化、29年10月に協同組合を設立。年間100回を超えるセミナーを行いながら全国を回り、仲間作りとグループ全体のスキルの向上、全国での案件の受注に努めている。
親愛信託・事業承継・相続対策・企業法務・開業支援
バイク・着物を着て(練習中)おでかけ