一覧
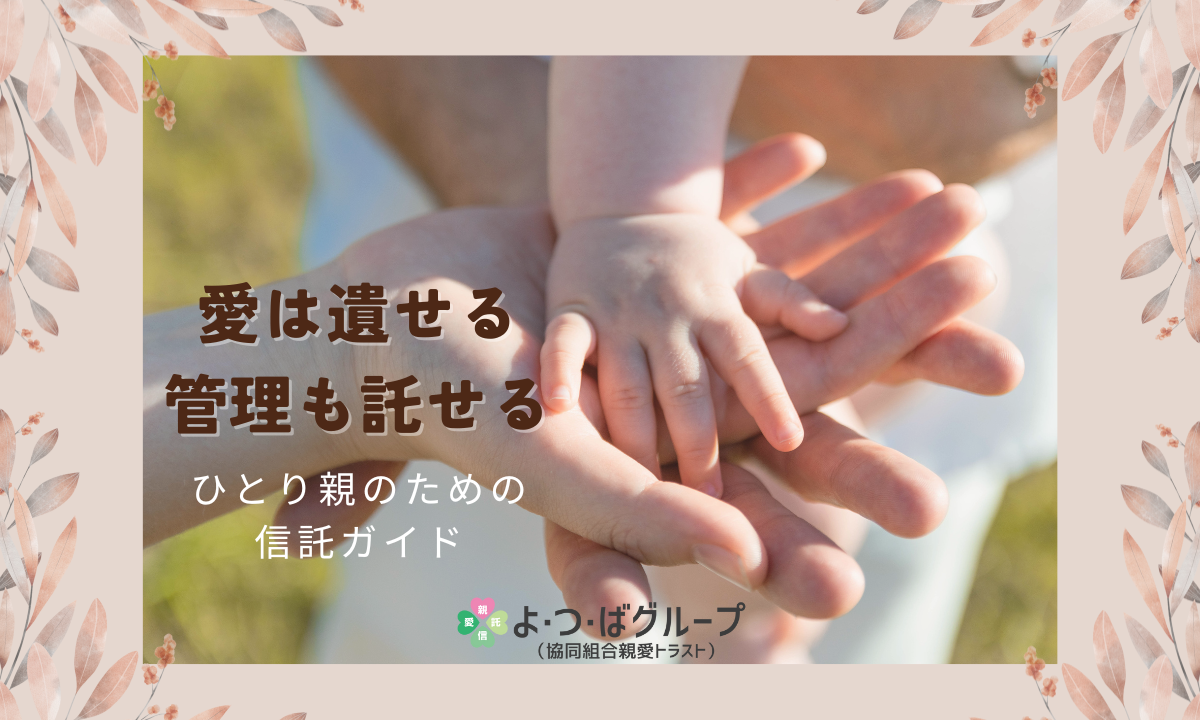
離婚や死別など事情があって子供をおひとりで育てている方(いわゆる「ひとり親世帯」)の数は、20年前に比べて1.3倍にもなっています。
2021年に行われた国勢調査によると、一般世帯が5,572万世帯あるのに対し、
・母子世帯はおよそ119.5万世帯
・父子世帯はおよそ14.9万世帯
という結果が出ています。特に父子家庭に関しては、ざっくり2倍近くにもなっており、シングルファザーが増えてきていることがわかります。
自分に「もしものこと」があった場合、財産と子供を残して逝ってしまうことになります。
財産がないと困りますが、「あっても困る」場合があるのです。
たとえば、財産がなくても生命保険に入っている方は多いのではないでしょうか。
ですが、生命保険も含めた財産を未成年の子供が相続すると「子供では管理できない」という問題が発生します。
未成年者の法律行為には、親の同意が必要なことがほとんどです。
不動産を相続し、売却したいとなった場合も親の同意が必要です。
ところが、その親が亡くなっているとなると、親の代わりに誰かを立てる必要があります。
ここで「もめごと」が起きやすくなります。
子供が多くの財産を相続した場合、それを狙って「自分が子供を育てるから親権を持ちたい」と言い出す人が現れたり、逆に「誰も親権者になりたがらない」というケースもあります。
亡くなった一人親のご両親(=おじいちゃんおばあちゃん)が元気な場合は、親権者になることも多いでしょうが、高齢だったり遠方だったりして、親権を担えないこともあります。
そして、周囲の人たちが一番困るのは「亡くなった親がどうしたかったのか分からない」ということです。
子供に財産を残したいと「遺言」を書いている方もいると思います。
ですが、若くして突然亡くなってしまうと、遺言を用意していないことも少なくありません。
私は、ひとり親家庭の親は最低限「遺言」は書いておくべきだと思います。
しかし、遺言だけだと未成年の子供が直接財産を持つことになってしまいます。
そこで活用したいのが「親愛信託」です。
もしもの時に、受益権という形で子供に財産を残すことができ、
子供自身がその財産を管理しなくても「収益のみを得ることができる」仕組みです。
また、誰に管理してほしいのかを事前に指定しておくことができます。
管理してほしい人に「こうしてほしい」と伝えておけるのも大きなメリットです。
たとえば:
・実際に子供の生活の世話(ご飯や洗濯など)は高齢のおじいちゃんおばあちゃんに頼みたい
・でも、財産管理は別の人に任せたい
そんなケースに親愛信託はぴったりです。
また、
・元配偶者に子供の面倒を見てもらっても、財産は管理させたくない
・もしくは逆に、財産管理は任せても子供には関わってほしくない
というケースでも親愛信託は活用できます。
例えば、明石家さんまさんと大竹しのぶさんのように、離婚しても仲良しだけど結婚生活は続けられないという夫婦もいますよね。
そうした場合に、亡くなった後で自分の親族が出てきて揉めないように、
事前に「もしもの時は、元配偶者が子供の財産を管理する」と決めておくことができます。
この時、元配偶者はあくまで「親愛信託の受託者」になるだけで、財産権そのものは子供のまま。
元配偶者に財産が渡ることはありません。
親愛信託では「財産を持つ人(受益者)」と「管理する人(受託者)」を別々に指定できます。
これを最大限に活かせば、思いもよらない人の手に管理が渡ったり、
もっとひどい場合には、全く渡したくない人に財産が渡ってしまう…なんてことを防げます。
ひとり親の場合、そうなる確率が高いうえに、実際に困るのは何より「子供」です。
生命保険については「生命保険信託」を使い、管理は信託会社に任せましょう。
親愛信託の場合は、「自己信託」という形でスタートさせ、
受益権を少しだけ子供に持たせ、自分の「次の受託者」を事前に決めておきます。
そうすることで、自分がいなくなった後は次の受託者に名義が変わり、その人が財産を管理するようになります。
年齢に関係なく、自分の大切な人のために、信託を活用してしっかり対策をしておくことが大事だと思います。
令和7年4月18日
協同組合親愛トラスト
代表 松尾陽子