信託の税務
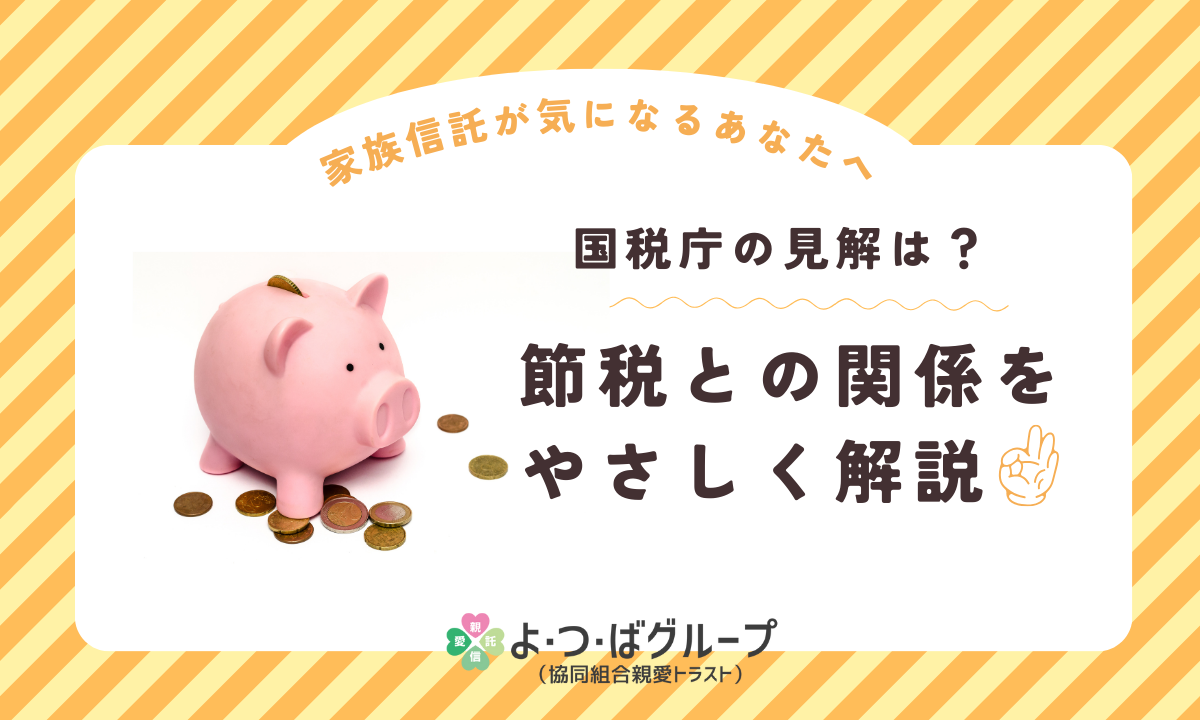
近年、信託は相続や認知症対策の場面で急速に認知が広まっています。
一方で、「信託で相続税が下がる」「信託すれば贈与税がかからない」など、誤った理解も拡散しています。
実際には、民事信託は税務上の取扱いに不公平が生じないよう、節税効果は基本的にありません。
これは国税庁も公式に明記しています。
民事信託の本質は、「財産管理の方法のひとつ」であり、「所有権の移転を目的とするもの」ではありません。
家族間における信託とは、財産の所有者(委託者)が、その財産の管理・運用・処分を家族等の信頼できる人(受託者)に託す制度です。
ポイントは、財産の経済的利益は「受益者」に属するという点にあります。
つまり、登記上の名義が変わっても、利益を享受する人が変わらなければ、税務上の取扱いも変わりません。
例えば、父が自宅やアパートを信託し、息子を受託者、自身を受益者とした場合。
財産の名義は息子になりますが、利益(家賃収入など)は父に帰属します。
このため、父が死亡した際には、信託財産は相続税の課税対象となります。
この仕組みは「受益者課税の原則」と呼ばれ、国税庁の見解として一貫しています。
また、節税どころか、逆に贈与税リスクが生じるケースもあります。
家族信託で受益者を変更した場合(例:父→子へ)、その時点で子に「経済的利益が移転した」と見なされ、原則的に贈与税が課税されます。
したがって、受益権を子や孫に変更する場合には、課税リスクを十分に検討する必要があります。
節税を目的とするなら、以下のような制度を併用する必要があります:
生前贈与(特例および非課税枠の活用)
生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人)
死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人)
配偶者控除や小規模宅地等の特例
家族間における信託は、他の制度と組み合わせて「財産を守るための方法」として利用すべきであり、単体では節税効果を期待すべきではありません。
家族信託はあくまでも、
認知症対策
承継の明確化
相続トラブル防止
といった「財産管理と意思の実現」が主目的です。
節税を期待して設計すると、税務リスクを生む逆効果になりかねません。
信託契約を結ぶ際は、身近な税理士や司法書士と連携し、「何を実現したいか」を明確にした上で、正確な税務知識に基づいた設計を行うことが肝要です。
令和7年5月23日
一般社団法人 京都民事信託協会
北條 達人