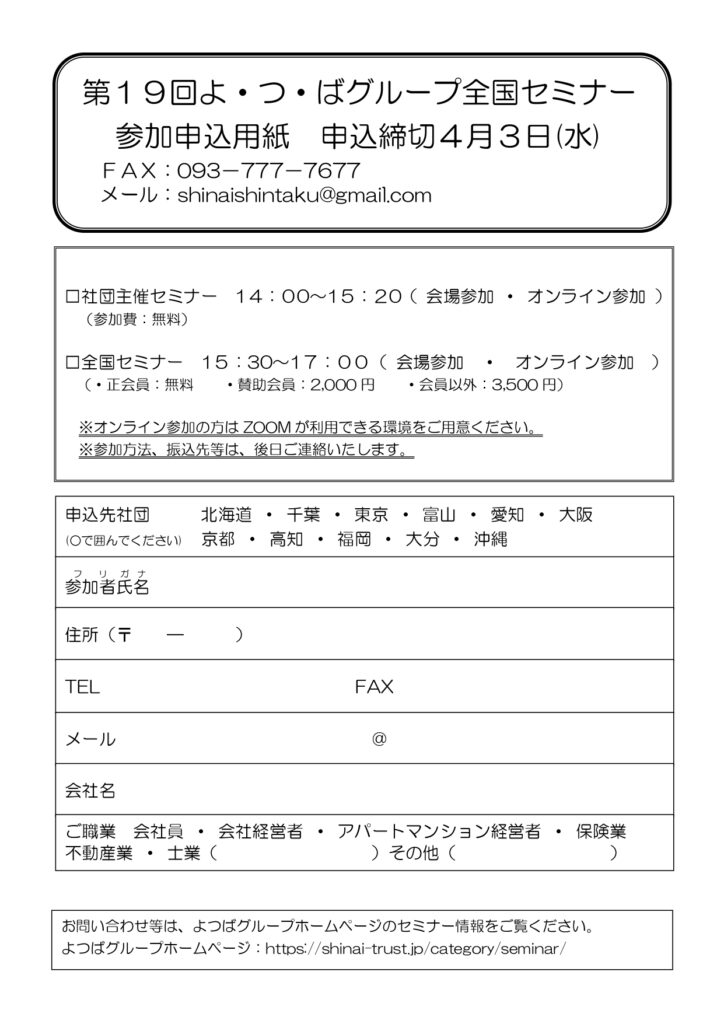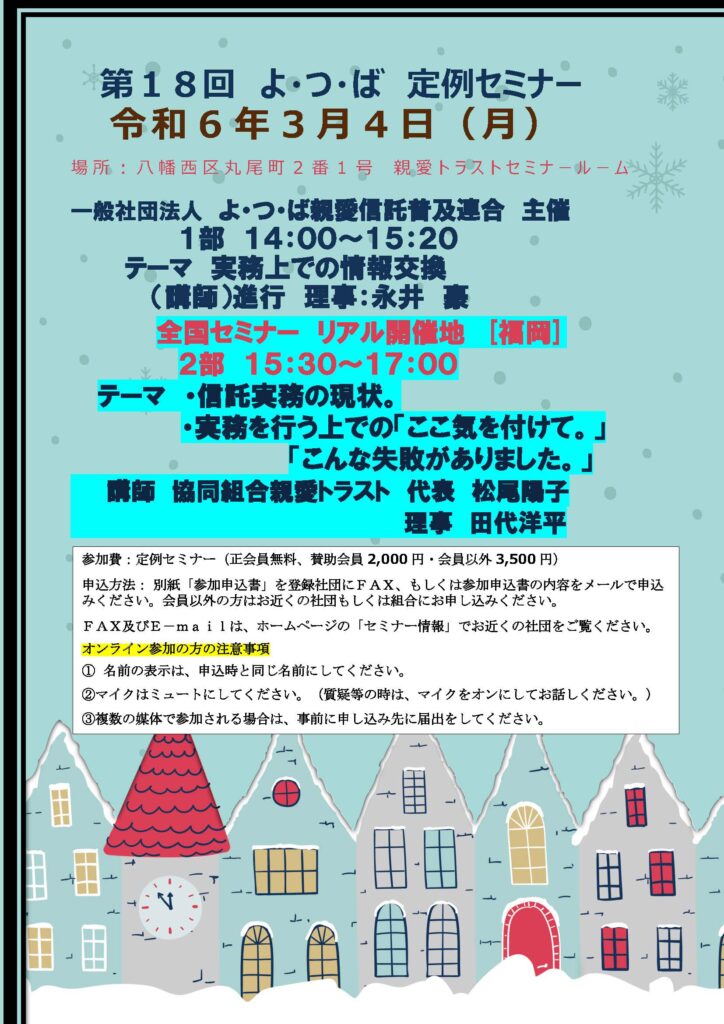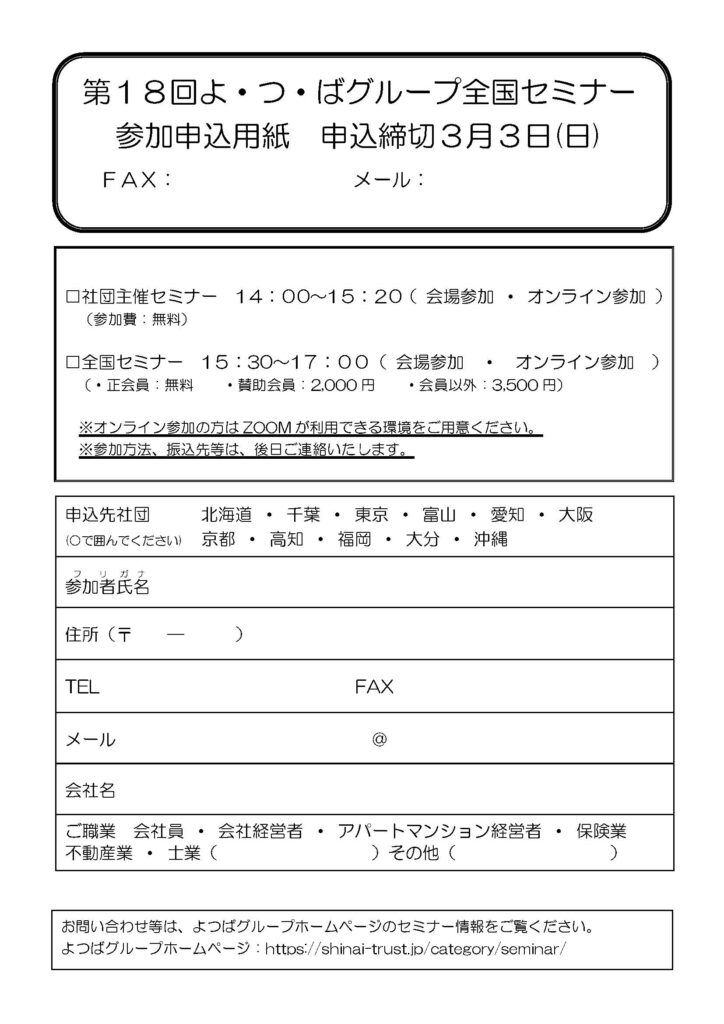新年明けましておめでとうございます。
2024年となり相続税・贈与税の改正が施行されました。
1)相続時精算課税に係る基礎控除の創設
2)暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し
1)相続時精算課税に係る基礎控除の創設
相続時精算課税の使い勝手が悪く、利用者が少なかったための改正かと思います。
今回の改正で、基礎控除が創設され、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円 が控除されます。
具体的には相続時精算課税制度を選択し、毎年110万円以内の贈与であれば贈与税がかかりません。
今までの歴年課税の控除と同じような扱いができます。
ただし、相続時精算課税制度を選択すると、歴年課税に戻すことはできません。
2)暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し
今回の改正で歴年課税の生前贈与の加算期間が長くなります。
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に その相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、 その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得 した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を 相続税の課税価格に加算することとされます。
現在所有の財産額と生命保険金額等を計算し、相続税がどの位かかりそうかを計算します。
生前贈与する場合、まず考えていただきたいのは、相続税率がどの位かです。
相続税率と贈与税率と比較して、贈与金額を決めましょう。
相続税率が大きければ、110万円の非課税金額にこだわらずに贈与税を払ってでも贈与した方が良い場合があります。
ここで贈与対象ですが、推定相続人(相続人となる方)に贈与するだけでなく、孫や子の配偶者等への贈与も検討しましょう。
これらの方は生前贈与の加算対象者ではないので、贈与しても相続時に相続財産に加算する持ち戻しにはなりません。
ただし、遺言で受贈者となっていたり、生命保険金の受取人になっている場合(みなし相続財産となる場合)は要注意です。持ち戻しの対象となります。
生前贈与する場合は、きちんとした証拠を残すことが大事です。
1)贈与契約書を贈与者・受贈者で作成する。
2)贈与契約書に公証役場で確定日付をつけてもらう。その日に存在していたことの証明となります。
3)贈与は預金口座に振り込みをする。
以上の手順を踏むことで証拠がきちんと残ります。
ここで、孫に贈与したら、すぐ使ってしまうからと気にする方がいらっしゃいます。
そのような場合は、贈与したお金を使えなくすることも大事です。
一つの方法は、生命保険契約をして贈与したお金を保険料に充当することで使えなくなります。
相続税対策はまだまだ他にもあります。
詳細は個別相談してください。
不明な点については相談してください。
一般社団法人よつば親愛信託大分 代表理事 阿部豊志
_page-0001-724x1024.jpg)